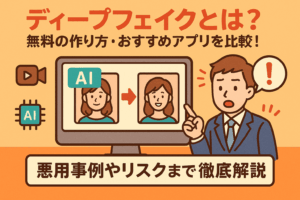えんぴっちょ
えんぴっちょ「頭の中には最高のイラストのイメージが浮かんでいるのに、それを形にするスキルや時間がない…」そんな悩みを抱えていませんか?自分の創造性を最大限に発揮したいと願う全てのイラストレーターやアーティストにとって、この悩みは大きな壁となります。もし、その壁を乗り越え、頭の中のイメージを瞬時に、そして美麗なアートとして生み出す方法があるとしたら、あなたの創作活動はどれほど豊かになるでしょうか。
この記事では、そんなあなたの悩みを解決する画期的なAI画像生成ツール「Stable Diffusion」について、その基本から具体的な使い方、さらには商用利用のポイントまで、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。
この記事を最後まで読めば、あなたもStable Diffusionを自在に操り、創作の限界を超えた新しい表現の世界へ飛び込むことができるでしょう。
Stable Diffusionとは?


Stable Diffusion(ステーブルディフュージョン)とは、2022年に公開されて以来、世界中のクリエイターを魅了している画像生成AIです。 イギリスのスタートアップ企業「Stability AI」によって開発され、入力したテキスト(プロンプト)をもとに、AIが自動で高品質な画像を生成してくれます。 例えば、「夕暮れの海辺を歩く少女、アニメ風」といった簡単な言葉を入力するだけで、まるでプロのイラストレーターが描いたような作品を生み出すことが可能です。
この技術の根幹には「拡散モデル(Diffusion Model)」という深層学習の技術が使われており、ノイズだらけの画像から少しずつノイズを除去していくことで、最終的に鮮明な画像を生成するという仕組みになっています。 これまでの画像生成AIと一線を画す最大の特徴は、ソースコードが一般公開されているオープンソースである点です。 これにより、誰でも無料で利用できるだけでなく、世界中の開発者が自由に改良やカスタマイズを加えることができ、日々進化を続けています。
Stable Diffusionの特徴とメリット
Stable Diffusionが多くのクリエイターから絶大な支持を得ているのには、明確な理由があります。その特徴とメリットを理解することで、あなたの創作活動にどのように活かせるかが見えてくるでしょう。
最大の魅力は、なんといっても基本的に無料で利用できる点です。 オープンソースであるため、コストを気にすることなく、好きなだけ画像生成を試すことができます。さらに、カスタマイズ性が非常に高いことも大きなメリットです。 世界中のユーザーが作成した「モデル」と呼ばれる追加学習データを導入することで、アニメ風、リアルな写真風、水彩画風など、自分の好きな画風の画像を自在に生成できます。
生成した画像の著作権は基本的に作成者に帰属するため、商用利用が可能な点も、プロのアーティストやビジネスでの活用を考える方にとって大きな強みです。 また、自分のパソコンに「ローカル環境」を構築すれば、インターネット接続なしで、生成枚数や表現の制限なく、心ゆくまで創作に没頭することが可能です。
他の画像生成AIとの違い
画像生成AIには、Stable Diffusionの他にも有名なものがいくつか存在します。特に「Midjourney」は、しばしば比較対象として挙げられます。あなたがどちらのツールを使うべきか判断できるように、それぞれの違いを比較してみましょう。
Midjourneyは、Discordというチャットアプリ上で手軽に利用でき、非常に高品質で芸術的な画像を簡単に生成できるのが特徴です。一方で、現在は無料プランがなく、利用するには月額料金が発生します。対してStable Diffusionは、前述の通り無料で利用でき、モデルや拡張機能によるカスタマイズの自由度が非常に高いのが強みです。アーティストが自分の作風を追求したり、特定のキャラクターを様々な構図で描いたりといった、細かな要求に応える力はStable Diffusionが優れていると言えるでしょう。
どちらが良いというわけではなく、手軽に美しいアートを創りたいならMidjourney、コストをかけずに自分だけの表現を追求したいならStable Diffusionというように、目的によって使い分けるのがおすすめです。
| Stable Diffusion | Midjourney | |
| 料金 | 基本的に無料(ローカル環境) | 有料(サブスクリプション制) |
| 使いやすさ | 設定がやや複雑だが、慣れれば自由自在 | 直感的で初心者でも操作しやすい |
| 画風の傾向 | モデル次第でリアル系からアニメ系まで幅広い | アート的、幻想的な作風が得意 |
| カスタマイズ性 | 非常に高い。モデルや拡張機能が豊富 | 限定的だが、簡単に高品質な画像が得られる |
| 商用利用 | 原則可能(利用モデルの規約による) | 有料プランに加入すれば可能 |



Stable Diffusionの使い方
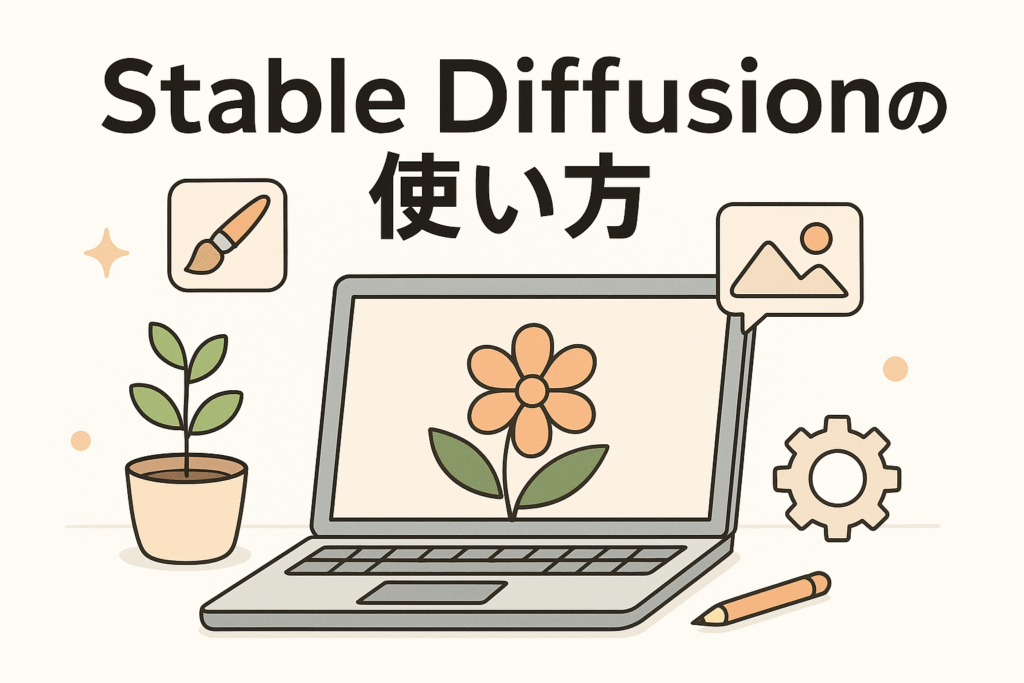
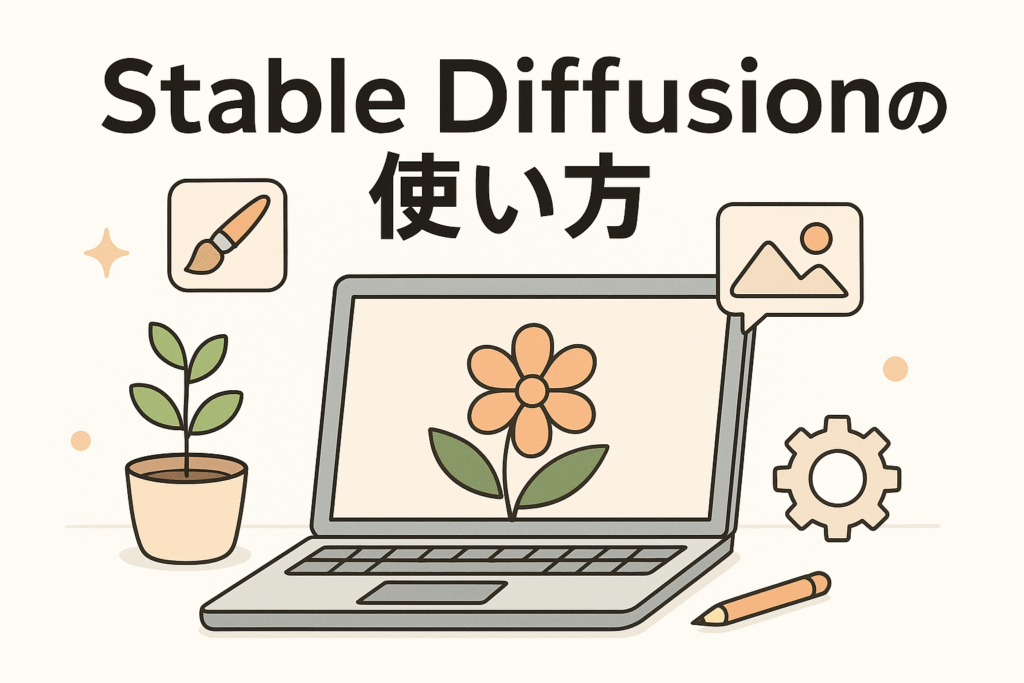
Stable Diffusionを始めるには、大きく分けて2つの方法があります。 一つは、Webブラウザ上で手軽に利用できる「Webサービス」を使う方法。もう一つは、自分のパソコンにプログラムをインストールして動かす「ローカル環境」を構築する方法です。
Webサービスは、パソコンのスペックを問わず、アカウントを登録するだけですぐに始められる手軽さが魅力です。 一方、ローカル環境は、導入に少し手間がかかりますが、生成枚数や機能の制限がなく、完全に無料で利用できるという大きなメリットがあります。あなたのスキルレベルや創作スタイルに合わせて、最適な方法を選んでみましょう。まずはWebサービスで色々試してみて、本格的に使いたくなったらローカル環境に挑戦するのがおすすめです。
Webサービスを利用する方法
「ハイスペックなパソコンは持っていないけど、すぐにでもStable Diffusionを試してみたい!」という方には、Webサービスの利用が最適です。 複雑なインストール作業は一切不要で、Webサイトにアクセスし、アカウントを登録するだけで、誰でも簡単に画像生成を始めることができます。
これから紹介するサービスは、いずれもStable Diffusionを基盤としており、手軽にその性能を体験できます。サービスによっては、無料で利用できる範囲に制限がある場合もありますが、まずはどのような画像が作れるのかを知る第一歩として、ぜひ活用してみてください。
Dream Studioの基本的な使い方
Dream Studioは、Stable Diffusionの開発元であるStability AIが公式に提供しているWebサービスです。公式サービスならではの安定感と、最新モデルをいち早く試せるのが魅力です。利用するにはアカウント登録が必要で、最初に無料のクレジットが付与されます。このクレジットを消費して画像を生成する仕組みです。
使い方は非常に直感的で、画面中央の入力欄に生成したい画像のイメージを英語で入力(プロンプト)し、「Dream」ボタンをクリックするだけです。 より凝った画像を作りたい場合は、画像のスタイルを選んだり、生成枚数を変更したり、避けたい要素(ネガティブプロンプト)を指定したりといった詳細設定も可能です。
| サービス名 | Dream Studio |
| 運営元 | Stability AI |
| 料金体系 | クレジット制(新規登録時に無料クレジット付与) |
| 特徴 |
|
Hugging Faceの活用方法
Hugging Face(ハギングフェイス)は、AIの開発者や研究者が集まる巨大なプラットフォームで、様々なAIモデルが公開・共有されています。その中の一つとして、Stable Diffusionを無料で試せるデモページが提供されています。
こちらもアカウント登録は不要で、サイトにアクセスすればすぐに利用できます。使い方はDream Studioと同様に、プロンプト入力欄に作りたい画像のキーワードを英語で入力し、生成ボタンを押すだけです。 Hugging Faceのデモは、あくまでも機能を試すためのシンプルなものですが、Stable Diffusionの基本を手軽に体験するには十分な機能を備えています。
| サービス名 | Hugging Face |
| 運営元 | Hugging Face, Inc. |
| 料金体系 | 無料 |
| 特徴 |
|
Mageで画像を作る手順
Mage.space(メイジ・スペース)も、Stable Diffusionを手軽に試せる無料のWebサービスです。 アカウント登録なしで利用でき、非常にシンプルなインターフェースが特徴です。サイトにアクセスしたら、画面中央の入力欄にプロンプトを英語で入力し、矢印ボタンを押すだけで画像が生成されます。
Mage.spaceの便利な点は、プロンプト入力欄の下に「避けたいイメージ(Negative Prompt)」を入力する欄が標準で用意されていることです。 これにより、例えば「低品質」「指が6本」といった、生成してほしくない要素を簡単かつ明確にAIへ伝えられ、画像のクオリティ向上に役立ちます。手軽に、しかし少しこだわった画像を作りたい場合に便利なサービスです。
| サービス名 | Mage.space |
| 料金体系 | 無料(一部機能は有料) |
| 特徴 |
|
ローカル環境で使う方法
あなたの創作意欲を完全に解放したいなら、自分のPCに「ローカル環境」を構築するのが最もおすすめの方法です。ローカル環境の最大のメリットは、Webサービスのような生成枚数や機能の制限が一切なく、完全に無料で心ゆくまで画像生成を楽しめることです。 世界中の有志が作成した無数のモデルや拡張機能を自由に追加し、あなただけの最高の画像生成環境を構築できます。
ただし、AIを動かすためにはある程度の性能を持つパソコン(特にグラフィックボードの性能が重要)が必要になり、最初の環境構築には少し手間がかかるというデメリットもあります。 ここでは、その導入手順をOS別に解説します。
Windows環境へのインストール方法
Windows PCにStable Diffusionのローカル環境を構築するには、いくつかの準備が必要です。 画像生成には高い計算能力が求められるため、NVIDIA製のグラフィックボード(GPU)を搭載し、そのビデオメモリ(VRAM)が最低でも8GB以上、快適に使うなら12GB以上あるPCが推奨されます。 準備ができたら、以下の手順でインストールを進めましょう。
- Pythonのインストール: まず、プログラミング言語であるPythonをインストールします。公式サイトからバージョン「3.10.6」をダウンロードするのが一般的です。
- Gitのインストール: 次に、ソースコードを管理するツールであるGitをインストールします。公式サイトからダウンロードして、手順に従いインストールしてください。
- Stable Diffusion Web UIのダウンロード: コマンドプロンプトを開き、専用のコマンドを実行して、Stable Diffusionを簡単に操作するためのツール(Web UI)をダウンロードします。
- 起動とアクセス: ダウンロードしたフォルダ内にある「webui-user.bat」というファイルを実行すると、自動で準備が進み、ブラウザで操作画面が開きます。
Mac環境へのインストール方法
Appleシリコン(M1, M2など)を搭載したMacでも、Stable Diffusionのローカル環境を構築することが可能です。Windowsと同様に、いくつかのツールを順番にインストールしていく必要があります。Macの場合は「Homebrew」というパッケージ管理ツールを使うと、必要なソフトウェアの導入がスムーズに進みます。 以下が、大まかな手順です。
- Homebrewのインストール: ターミナルを開き、Homebrew公式サイトにあるコマンドをコピー&ペーストして実行し、Homebrewをインストールします。
- 必要パッケージのインストール: Homebrewを使い、Stable Diffusionの実行に必要となる複数のパッケージ(cmake, protobuf, rustなど)を一つのコマンドでまとめてインストールします。
- Stable Diffusion Web UIのダウンロード: ターミナルからGitコマンドを使い、操作ツールであるStable Diffusion Web UI本体をPCにダウンロードします。
- 起動とアクセス: ダウンロードしたディレクトリに移動し、起動用のスクリプト(./webui.sh)を実行します。 初回起動には時間がかかりますが、完了するとブラウザで操作画面にアクセスできます。
Google Colabで利用する手順
「自分のPCのスペックに自信がない…でもローカル環境のように自由にカスタマイズしてみたい!」という方に最適なのが、Google Colabを利用する方法です。 Google Colabは、Googleが提供するクラウド上の仮想マシンで、高性能なGPUをブラウザ経由で利用できるサービスです。 これを使えば、自分のPCの性能に関わらず、Stable Diffusionを動かすことができます。Googleアカウントさえあれば、誰でも始められます。
使い方は、Stable Diffusionを実行するためのプログラムが書かれた「ノートブック」ファイルを開き、上から順番に実行ボタンをクリックしていくだけです。 専門的な知識はあまり必要ありませんが、無料版には連続使用時間などの制限がある点には注意が必要です。



Stable Diffusion Web UIの活用方法


Stable Diffusionの真価は、ローカル環境で「Stable Diffusion Web UI」というツールを使うことで最大限に発揮されます。これは、ブラウザ上で直感的に画像生成を操作できるインターフェースで、プロンプト入力はもちろん、モデルの切り替えや拡張機能の追加など、あらゆるカスタマイズの中心地となります。
特に、特定の画風を学習した「モデル」や、キャラクター・服装などを後から追加できる「LoRA」、そしてポーズや構図を細かく指定できる「ControlNet」といった機能を使いこなすことが、あなたの創作を次のレベルへと引き上げる鍵です。 これから、これらの代表的な活用方法を一つずつ解説していきます。これらの技術を組み合わせることで、もはや偶然に頼るのではなく、あなたの頭の中にあるイメージを的確に、そして高精度にビジュアル化することが可能になるでしょう。
AUTOMATIC1111版とForge版の特徴比較
Stable Diffusion Web UIには、最も広く使われている「AUTOMATIC1111版」と、それをベースに最適化された「Forge版」の2種類が主流です。 AUTOMATIC1111版は、豊富な拡張機能と膨大な情報量で、長年にわたり多くのユーザーに支持されてきました。
一方、後発のForge版は、AUTOMATIC1111版のUIや機能をほぼ引き継ぎつつ、画像生成の高速化とVRAM(ビデオメモリ)使用量の削減を実現しているのが大きな特徴です。 これにより、グラフィックボードの性能がそれほど高くないPCでも、より快適に画像生成を行えるようになりました。 どちらを選ぶかは好みにもよりますが、これからローカル環境を構築するなら、基本的には高速で軽量なForge版から試してみるのがおすすめです。
| AUTOMATIC1111版 | Forge版 | |
| 特徴 | 最も普及している標準的なWeb UI 拡張機能や情報が豊富 | AUTOMATIC1111版の最適化版 高速な画像生成と省メモリが強み |
| メリット |
|
|
| デメリット | Forge版に比べると動作が重い | 一部の古い拡張機能が動かない可能性 |
| おすすめのユーザー | 安定性を重視し、既存の資産を活かしたい方 | これから始める方、より快適な環境を求める方 |
モデルファイル(Checkpoint)の導入方法
モデルファイル(チェックポイント)は、Stable Diffusionにおける画風の基盤となる最も重要なファイルです。 実写のようなリアルな画像を得意とするモデルや、特定のアニメ風のイラストに特化したモデルなど、世界中のクリエイターが作成した無数のモデルが存在します。 これらを切り替えることで、あなたはプロンプトを変えることなく、全く異なるテイストの作品を生み出せるのです。
モデルは主に「Civitai」や「Hugging Face」といったサイトで配布されており、気に入ったものを見つけたらダウンロードします。 導入方法は非常に簡単で、ダウンロードしたモデルファイル(拡張子が.safetensorsや.ckpt)を、あなたのStable Diffusion Web UIのフォルダ内にある「models」→「Stable-diffusion」というフォルダに入れるだけです。 これで、Web UIの画面左上にあるドロップダウンリストから、いつでも好きなモデルを選んで使えるようになります。
追加学習モデルLoRAの活用方法
「このキャラクターのまま、違う衣装を着せたい」「この画風に、特定のポーズを組み合わせたい」そんな願いを叶えるのが「LoRA(Low-Rank Adaptation)」です。 LoRAは、ベースとなるモデル(チェックポイント)に対して、キャラクターの服装や髪型、特定の画風、ポーズといった要素を追加学習させた「差分ファイル」のようなものです。
モデル本体と比べてファイルサイズが非常に小さく、手軽に導入できるのが大きな魅力です。 複数のLoRAを組み合わせることも可能で、例えば「キャラクターAのLoRA」+「サイバーパンク風の服装のLoRA」+「見返りポーズのLoRA」といったように、細かな要素を自在に掛け合わせることができます。 使い方は、モデルと同様に「Civitai」などでLoRAファイルをダウンロードし、「models」→「Lora」フォルダに保存。 Web UIのプロンプト入力欄の下にある「Lora」タブから使いたいものをクリックするだけで、プロンプトに自動で適用されます。
ControlNetを使った画像調整方法
「キャラクターのポーズがなかなか思い通りにならない」というのは、画像生成AIを使う上で多くの人が直面する壁です。この悩みを解決してくれるのが、拡張機能「ControlNet」です。ControlNetは、参照する画像から輪郭線や人物の骨格(ポーズ)などを抽出し、その情報を維持したまま新しい画像を生成する技術です。
例えば、あなたが描いたラフな棒人間のイラストを読み込ませ、そのポーズを忠実に再現したキャラクターを生成させることができます。 また、写真からポーズだけを抜き出して、全く違うキャラクターに同じポーズをさせることも可能です。 これにより、プロンプトだけでは困難だった複雑な構図や、意図した通りのポージングを極めて高い精度でコントロールできるようになります。 あなたの創作における表現の自由度を、飛躍的に向上させてくれる強力なツールと言えるでしょう。



Stable Diffusionの画像を商用利用する際の注意点


Stable Diffusionはオープンソースであり、生成した画像は基本的に商用利用が可能です。 これにより、あなたの作品を販売したり、企業の広告素材として活用したりと、創作活動の幅を大きく広げることができます。しかし、「何でもかんでも自由に使える」というわけではありません。
トラブルを未然に防ぎ、安心して創作活動に打ち込むためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。特に、使用する「モデル」や、元にする「画像」のライセンス(利用規約)が商用利用を許可しているかどうかを確認することが不可欠です。 ここでは、アーティストとして知っておくべき商用利用のルールについて、具体的に解説していきます。
Stable Diffusionで生成した画像は商用利用できる?
結論から言うと、Stable Diffusionで生成した画像は、多くの場合で商用利用が可能です。 Stable Diffusion自体のライセンスは、非商用・商用を問わず幅広い利用を認めています。 これは、イラストレーターやアーティストが自身の作品を商品化したり、クライアントワークに活用したりする上で非常に大きなメリットです。
ただし、これはあくまで基本原則です。実際の利用にあたっては、あなたが使用するWebサービスや、ローカル環境で導入するモデル、そしてLoRAなどの追加学習ファイルに設定されている個別のライセンス規約を必ず確認する必要があります。 これらの規約で商用利用が禁止されている場合、それに従って生成した画像も商用利用はできなくなるため、注意が必要です。
商用利用がNGになるケース
Stable Diffusionの自由度の高さは魅力的ですが、意図せず権利を侵害してしまうリスクも潜んでいます。 安心して創作活動を行うために、どのような場合に商用利用がNGとなるのか、具体的なケースをしっかりと把握しておきましょう。主に問題となるのは、元となるデータに他者の権利が含まれている場合です。これを知らずに使ってしまうと、後々大きなトラブルに発展しかねません。ここでは、特に注意すべき代表的な2つのケースについて詳しく解説します。
商用利用不可の画像を元に生成した場合
Stable Diffusionには、既存の画像を元に新しい画像を生成する「img2img」という機能があります。これは、構図や色合いの参考にしたり、ラフ画から清書したりする際に非常に便利な機能です。しかし、この元画像に著作権が存在する場合、注意が必要です。
例えば、インターネット上で見つけたアニメのキャプチャ画像や、他人が描いたイラストなどを無断でimg2imgの元画像として使用し、生成した画像を販売する行為は、元の作品の著作権を侵害する可能性が非常に高くなります。 商用利用を考えている場合は、必ず著作権フリーの素材や、自身で撮影・作成したオリジナルの画像を使用するようにしましょう。
商用利用不可のモデルを利用した場合
商用利用の可否を判断する上で最も重要なのが、使用するモデル(チェックポイント)やLoRAのライセンスです。これらのモデルは世界中のユーザーによって作成・公開されており、それぞれに異なる利用規約が設定されています。
モデルの配布ページ(Civitaiなど)には、通常「Allows commercial use(商用利用を許可)」といったアイコンや説明書きがあります。 ここで「No」とされているモデルや、「No selling images(画像の販売禁止)」といった明確な記載があるモデルを使用して生成した画像は、当然ながら商用利用することはできません。 あなたの作品を守るためにも、モデルをダウンロードする際には、必ずライセンス情報を確認する習慣をつけましょう。



Stable Diffusionに関するよくある質問


ここでは、Stable Diffusionをこれから始めようとする方や、使い始めたばかりの方が抱きやすい疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。無料で使えるのか、日本語には対応しているのか、といった基本的な質問から、より快適に使うためのツールの知識まで、あなたの疑問を解消します。
Stable Diffusionは無料で利用可能か?
はい、基本的に無料で利用できます。 Stable Diffusionはオープンソースのソフトウェアとして公開されているため、プログラム自体にお金はかかりません。 自分のPCにローカル環境を構築すれば、性能が許す限り、完全に無料で好きなだけ画像を生成し続けることが可能です。ただし、手軽に試せるWebサービスの中には、無料プランでは生成枚数に制限があり、無制限に使うには有料プランへの登録が必要な場合もあります。
日本語で細かい指示を出すことはできるか?
プロンプト(指示文)は英語で入力するのが基本ですが、日本語に対応させる方法もあります。 多くのWeb UIには翻訳機能が内蔵されていたり、拡張機能を追加することで、プロンプトを日本語で入力しても自動で英語に翻訳してAIに伝えてくれたりします。 ただし、翻訳の精度によっては意図したニュアンスが伝わりにくい場合もあるため、より複雑で細かい指示を出したい場合は、DeepLなどの高精度な翻訳サービスを使いながら、英語のプロンプトを作成するのがおすすめです。
Stable Diffusion Web UIとは何か?
Stable Diffusion Web UIとは、Stable DiffusionをWebブラウザ上で簡単に操作できるようにするためのツール(ユーザーインターフェース)のことです。 プログラムの専門知識がない人でも、プロンプトの入力やモデルの切り替え、各種パラメータの調整などを直感的に行えるように設計されています。 最も有名な「AUTOMATIC1111版」をはじめ、その最適化版である「Forge」など複数の種類があり、ローカル環境でStable Diffusionを使う際の標準的なツールとなっています。
画像生成にプロンプトの入力数制限はあるか?
厳密には、プロンプトの入力文字数自体に明確な上限はありません。しかし、AIが一度に処理できる情報の量には限界があります。この処理単位を「トークン」と呼び、多くのStable Diffusion Web UIでは、75トークンを1ブロックとして処理します。一般的に、75トークンを超えたプロンプトも入力可能ですが、長すぎると後半部分が無視されたり、効果が薄れたりすることがあります。 重要なキーワードはできるだけ前方に配置し、簡潔に記述することを意識すると良いでしょう。



Stable Diffusionについてのまとめ
この記事では、画像生成AI「Stable Diffusion」の基本から、具体的な使い方、さらには商用利用の注意点までを詳しく解説してきました。Stable Diffusionは、無料で利用できるオープンソースでありながら、モデルやLoRA、ControlNetといった豊富なカスタマイズ機能によって、あなたの創造性を無限に広げる可能性を秘めています。
はじめはWebサービスで手軽にその性能を体験し、慣れてきたらぜひローカル環境の構築に挑戦してみてください。最初は少し難しく感じるかもしれませんが、一度環境を整えてしまえば、そこはあなただけの自由なアトリエとなります。
この記事を参考に、あなたの中に眠るアイデアを次々と形にし、これまでにない新たなアート作品を生み出してみてください。あなたのクリエイターとしての可能性は、Stable Diffusionと共に、さらに大きく花開くことでしょう。