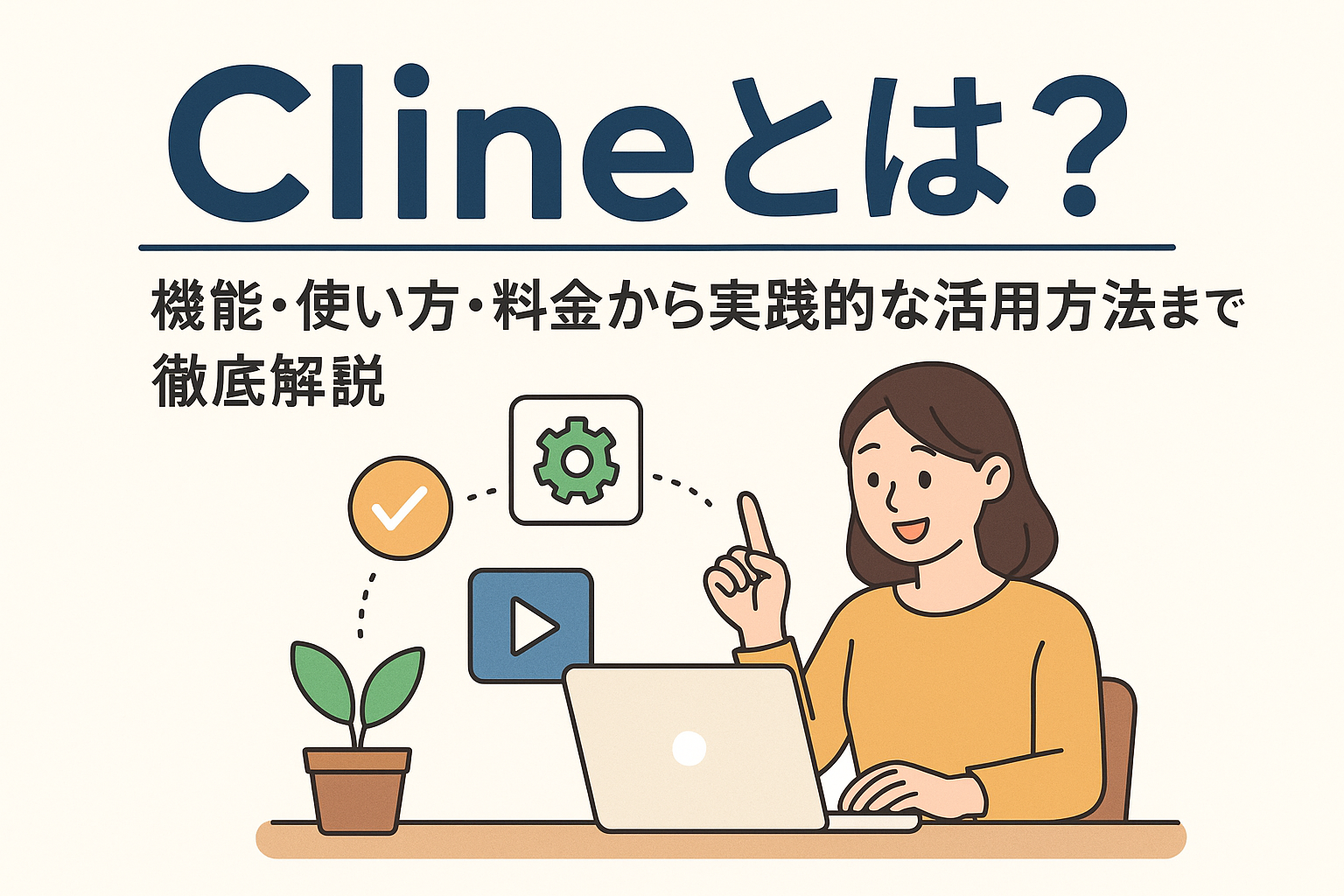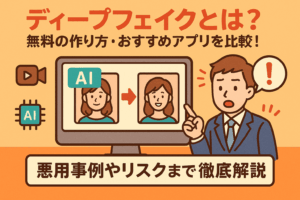えんぴっちょ
えんぴっちょ日々の開発業務で、プロジェクトのセットアップや定型的なコーディングに追われ、もっと創造的な作業に時間を使いたいと感じていませんか。同じコマンドを何度も入力したり、ファイルの作成や修正に手間取ったりするのは、非常にもったいないことです。そんな開発者の悩みをAIの力で解決するのが、今回紹介する「Cline」です。
この記事では、Clineがどのようなツールで、何ができるのか、基本的な概要から具体的な使い方、気になる料金体系まで、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説していきます。Clineを導入することで、これまで手作業で行っていた面倒なタスクを自動化し、あなたの開発効率を飛躍的に向上させることができるでしょう。さあ、あなたもClineを使いこなし、ワンランク上の開発者を目指しませんか。
【この記事でわかること】
- Clineとは?特徴や機能を詳しく解説
- Clineの実際の使い方をステップ別に紹介
- Clineの料金体系について解説
- Clineの種類とそれぞれの特徴を紹介
- Clineの拡張性・カスタマイズ機能を徹底解説
- Clineを活用する際に役立つTips
- Clineを使う際の課題と注意点
- Clineに関するよくある質問
- まとめ|Clineの特徴と活用方法を理解しよう
Clineとは?特徴や機能を詳しく解説
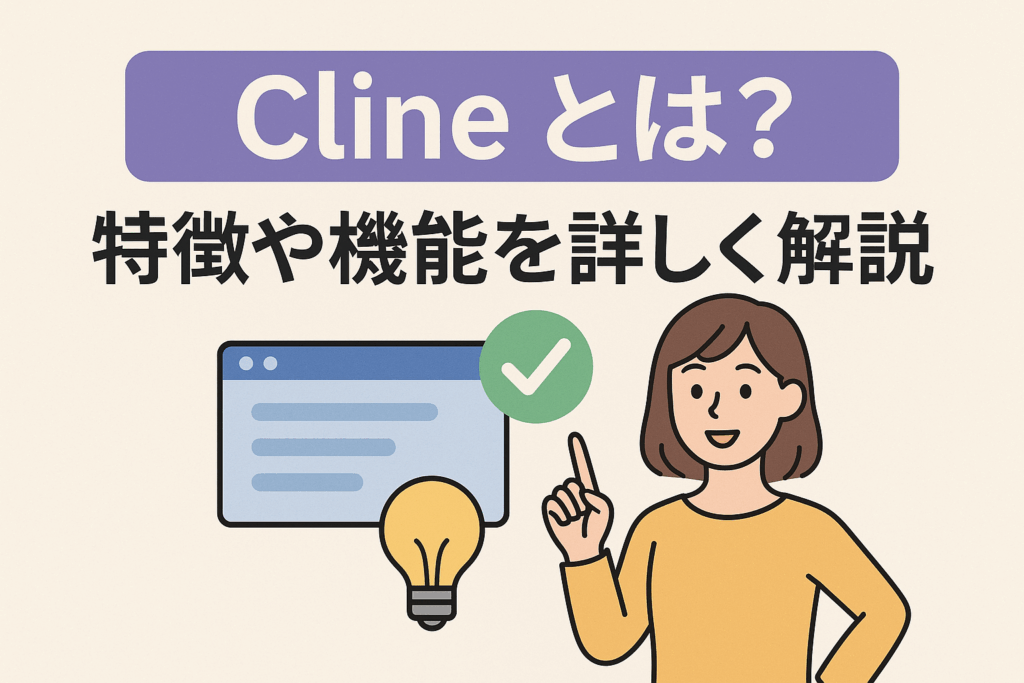
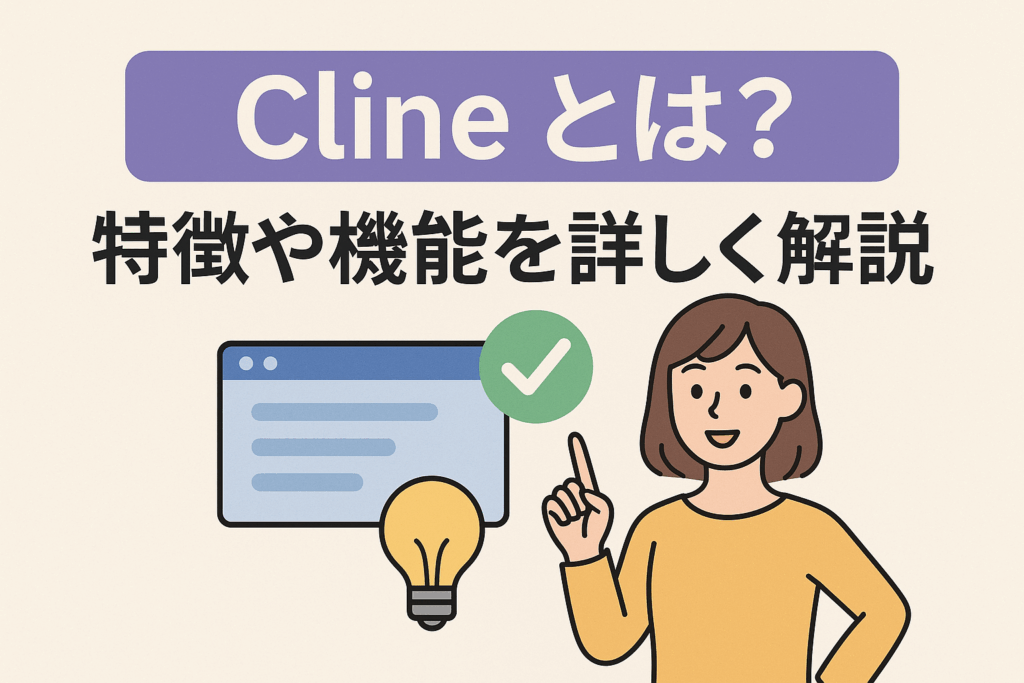
Clineとは、Visual Studio Code(VSCode)などの使い慣れたエディタ上で動作する、AIエージェント型の拡張機能です。 単にコードを提案するだけでなく、開発者の指示に基づき、自律的にタスクを遂行する能力を持っています。
例えば、「ユーザー管理機能を追加して」と指示するだけで、必要なファイルの作成からコードの記述、さらには動作確認までを自動で行おうとします。 これまで時間を要していた作業をAIに任せることで、開発者はより本質的でクリエイティブな業務に集中できるようになるのです。
タスクを駆動する効率的なAI支援
Clineの最大の特徴は、単なるコード補完ツールにとどまらない「タスク駆動型」のAI支援能力にあります。 従来のAIアシスタントが、人間のコーディングを補助する役割だったのに対し、ClineはAIが主体となって開発作業を進める「AIエージェント」として機能します。
具体的には、ユーザーが自然言語で指示を出すと、Clineはその意図を汲み取り、タスク完了までの計画を立て、コードの生成、修正、そしてターミナルでのコマンド実行までを自動的に行います。 まるで経験豊富な開発者が隣でペアプログラミングをしてくれるかのように、一連の開発フローをシームレスにサポートしてくれるのです。
複数AIモデル・APIとの連携が可能
Clineは、特定のAIモデルに依存せず、多様な選択肢から自由に連携先を選べる高い柔軟性を持っています。 OpenAIのGPTシリーズやAnthropicのClaude、GoogleのGeminiなど、主要なAIモデルに対応しており、プロジェクトの要件やコストに応じて最適なモデルを切り替えて利用することが可能です。
例えば、高度な推論が求められる設計段階では高性能なモデルを使用し、単純なコード生成ではコストパフォーマンスに優れたモデルを選ぶといった使い分けができます。 このように、AIモデルを自由に選択できる点は、開発の生産性とコスト管理の両面で大きなメリットと言えるでしょう。
ブラウザを統合してのデバッグ支援
Clineは、エディタ内でのコーディングだけでなく、ブラウザと連携したデバッグ作業も強力に支援します。 具体的には、Clineが内部的にブラウザを起動し、開発中のWebアプリケーションの表示を確認したり、ボタンのクリックなどの操作を自動で行ったりすることが可能です。
例えば、「このフォームを送信して、エラーメッセージが表示されるか確認して」と指示するだけで、Clineがブラウザ操作を実行し、その結果やコンソールログを解析してくれます。 これにより、コードの修正から実際の動作確認、そしてデバッグまでの一連のサイクルを、エディタから離れることなく、より高速に回すことができるようになります。
ファイルの作成・編集・差分管理機能
Clineは、ローカル環境にあるファイルを直接、作成・編集する強力な権限を持っています。 ユーザーが「新しいAPIエンドポイントのファイルを作成して」と指示すれば、Clineはプロジェクトの構造を解析し、適切な場所に新しいファイルを生成します。
さらに、既存のコードを修正する際には、変更前と変更後の差分(diff)を提示してくれるため、ユーザーはAIによる変更内容を正確に把握し、承認または却下することができます。 この差分管理機能により、意図しない変更が加えられるリスクを低減し、安心してAIにファイル操作を任せることが可能になります。
ターミナルでのコマンド実行サポート
開発作業において、ライブラリのインストールやビルド、テストの実行など、ターミナル操作は不可欠です。Clineは、これらのコマンド実行もAIエージェントが代行してくれます。
例えば、新しいプロジェクトを開始する際に必要なライブラリをインストールするよう指示すると、Clineは「npm install を実行しますか?」とユーザーに確認を求め、承認されれば自動でコマンドを実行します。 これにより、開発者はエディタとターミナルを頻繁に行き来する必要がなくなり、コーディング作業に集中できる環境が整います。まさに、開発ワークフロー全体を効率化する画期的な機能です。



Clineの実際の使い方をステップ別に紹介


ここからは、Clineを実際に利用するための手順を具体的に解説していきます。 インストールから初期設定、基本的な操作方法まで、ステップバイステップで進めていくので、初めての方でも安心して 따라올 수 있습니다。このセクションを読み終える頃には、あなたもClineを自在に操り、開発効率を劇的に向上させる第一歩を踏み出していることでしょう。
- 1. Clineのインストール方法
- 2. 初期設定の手順とポイント
- 3. コードの生成や修正を行う方法
- 4. ターミナルを使った操作方法
- 5. ブラウザを使ったデバッグの具体例
- 6. カスタムツールを追加する手順
- 7. 結果を正確に確認する方法
1. Clineのインストール方法
Clineの導入は非常に簡単です。 お使いのVisual Studio Code(VSCode)やCursorのエディタから直接インストールできます。
まず、エディタの左側にあるメニューから「拡張機能」のアイコンをクリックしてください。 次に、表示された検索バーに「cline」と入力します。 検索結果のリストにClineが表示されたら、「インストール」ボタンを押すだけで導入は完了です。
インストールが成功すると、サイドバーにClineのアイコンが新しく表示され、すぐに利用を開始できます。
2. 初期設定の手順とポイント
Clineをインストールしたら、次に行うのはAIモデルと連携させるための初期設定です。まず、サイドバーに追加されたClineのアイコンをクリックして設定画面を開きます。 ここで、「API Provider」というドロップダウンメニューから、利用したいAIサービス(例:Anthropic, OpenAIなど)を選択してください。
選択後、対応するAPIキーを入力する欄が表示されるので、事前に取得しておいた自身のAPIキーを貼り付けます。 最後に「Let’s go!」ボタンをクリックすれば設定は完了し、ClineがAIの力を借りて動作する準備が整います。
3. コードの生成や修正を行う方法
Clineを使えば、自然言語で指示するだけで簡単にコードの生成や修正ができます。 例えば、新しいプロジェクトで「Reactでカウンターアプリのコンポーネントを作って」とチャットで入力するだけで、Clineは必要なコード一式を自動で生成してくれます。
また、既存のコードに対して「この関数にエラーハンドリング処理を追加して」のように具体的な修正を依頼することも可能です。 Clineは文脈を理解し、適切な修正案を提示してくれます。このように対話形式で開発を進められるため、コーディングの速度が格段に向上するでしょう。
4. ターミナルを使った操作方法
Clineは、ターミナルコマンドの実行もチャット画面からの指示で行えます。 例えば、プロジェクトに必要なライブラリをインストールしたい場合、「expressをインストールして」と入力するだけです。Clineはこれを解釈し、「`npm install express` を実行しますか?」といった形で実行確認を求めてきます。
ユーザーが承認すると、実際にターミナルでコマンドが実行され、その結果がフィードバックされます。これにより、コマンドを記憶したり、手動で入力したりする手間が省け、よりスムーズに開発を進めることが可能になります。
5. ブラウザを使ったデバッグの具体例
Clineの強力な機能の一つが、ブラウザ操作を伴うデバッグの自動化です。 例えば、開発中のWebアプリケーションに対して「アプリを起動してテストを実行して」と指示するだけで、Clineは開発サーバーを立ち上げ、ブラウザでページを開き、エラーがないかを確認します。
もしブラウザのコンソールにエラーが出力された場合、Clineはその内容を読み取り、「このエラーを修正しますか?」と具体的なコードの修正案まで提示してくれます。 このように、コードの実行からブラウザでの動作確認、エラー修正までの一連の流れを、すべてAIが自律的に行ってくれるのです。
6. カスタムツールを追加する手順
Clineは、Model Context Protocol(MCP)という仕組みを通じて、機能を自由に拡張できる点も魅力です。 これにより、独自のコマンドや外部サービスとの連携(例えばJiraやNotionの操作)をカスタムツールとして追加できます。
例えば、「Jiraから未完了のチケットを取得するツールを追加して」と自然言語で指示するだけで、Clineがツール作成のプロセスを自動で進めてくれるのです。 作成したカスタムツールは保存され、以降の開発作業でいつでも再利用可能になります。 これにより、個々の開発ワークフローに最適化された、自分だけの強力な開発環境を構築できます。
7. 結果を正確に確認する方法
AIが自動で生成・修正したコードを、鵜呑みにするのは危険です。Clineは、AIによる変更点をユーザーが正確に確認できる仕組みを備えています。コードを修正する際には、必ず変更前と変更後の差分(diff)形式で内容を提示してくれます。
ユーザーはこの差分表示を見て、AIの提案が本当に正しいか、意図しない変更が含まれていないかを慎重にレビューすることが重要です。この確認作業を徹底することで、AIの力を安全に活用し、コードの品質を担保しながら開発効率を高めることができます。



Clineの料金体系について解説
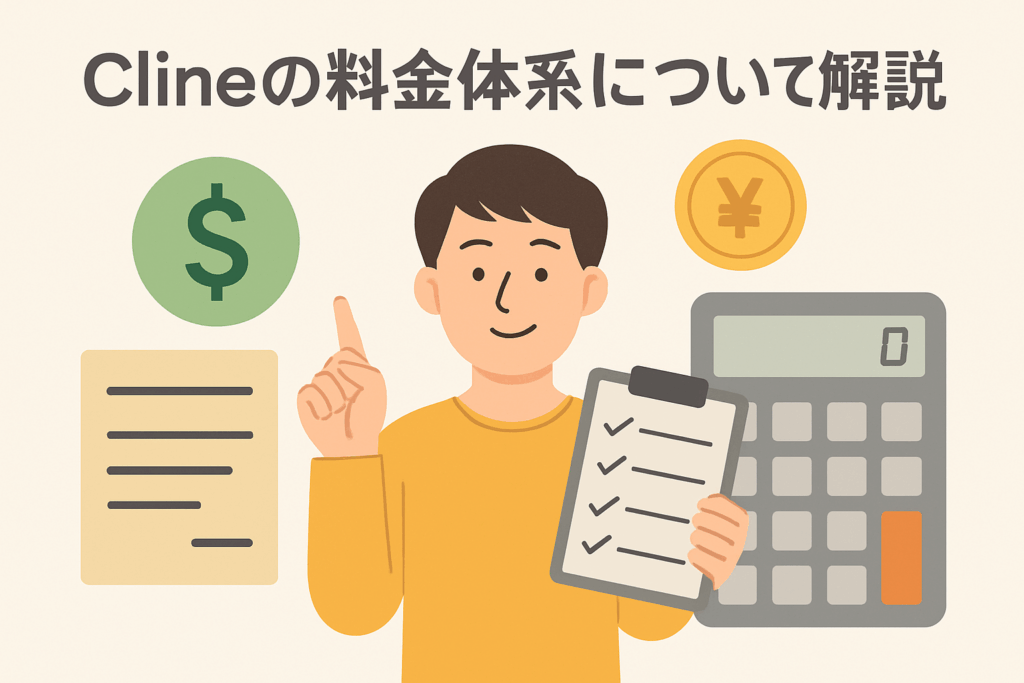
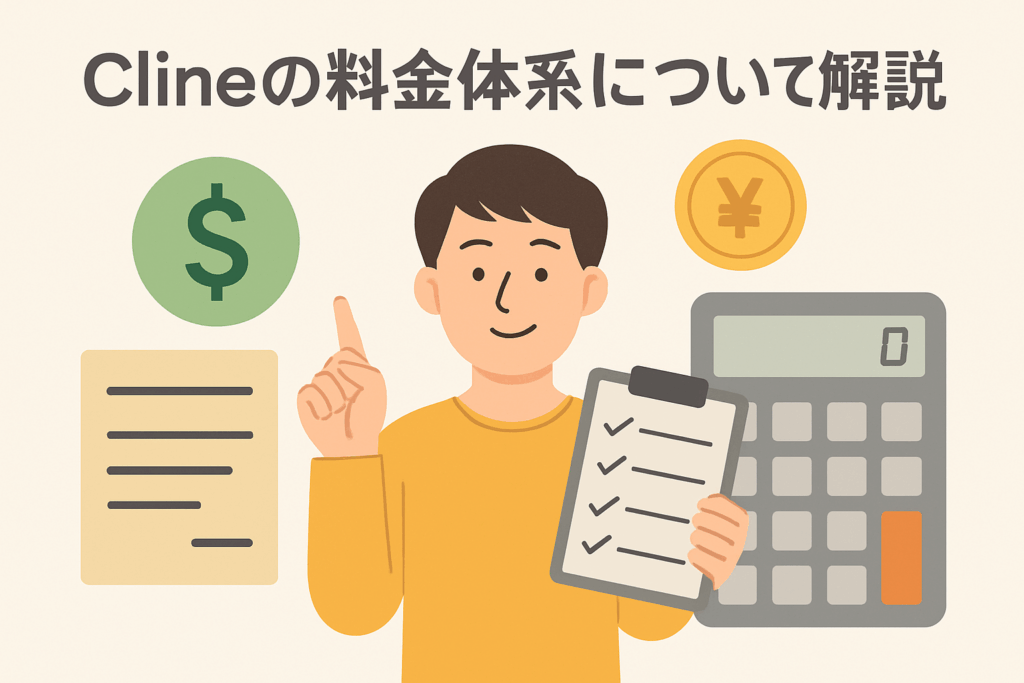
Clineを導入する上で、最も気になる点の一つが料金体系でしょう。 ここでは、Clineの利用にかかる費用について詳しく解説します。
Clineのツール自体は無料で利用できますが、その心臓部であるAIモデルの利用には別途コストが発生する仕組みです。 料金の仕組みを正しく理解し、コストを意識しながら賢く活用することが、長期的にClineを使いこなすための鍵となります。
Clineの基本料金と追加費用の目安
Clineの拡張機能自体は、オープンソースとして開発されており、無料でインストールして利用できます。 しかし、実際にコード生成などの機能を使うには、外部のAIモデルのAPIを呼び出す必要があります。 このAPIの利用料が、実質的なClineの利用コストとなります。
料金は、選択するAIモデルやプロバイダー(OpenAI, Anthropicなど)と、処理したテキスト量(トークン数)に応じた従量課金制です。 高性能なモデルほど料金は高くなる傾向があるため、タスクに応じてモデルを使い分けることがコスト管理のポイントです。
| 項目 | 料金 |
| Cline本体の利用料 | 無料 |
| API利用料 | 使用するAIモデルと使用量に応じた従量課金 |
| 料金の目安 | モデルや使い方により大きく変動(数円〜) |
| コストを抑える方法 | 安価なAPIモデルの利用、不要な処理を避ける |
実際にかかった料金例(DeepSeekを使った場合)
コストを抑えたい場合、比較的安価なAPIを提供しているDeepSeekのようなモデルを選択するのが有効な選択肢です。 あるユーザー事例では、Lambdaで動作するPythonコードの作成をほぼ全てClineに任せたケースで、かかった料金はわずか0.01ドル(日本円で数円程度)だったと報告されています。
この時のトークン使用量は、入力が約50万、出力が約7,000トークンだったとのことです。 もちろん、これはあくまで一例であり、タスクの複雑さや規模によって料金は変動しますが、安価なモデルを選べば非常に低コストで運用できる可能性を示しています。
| タスク | Lambda用Pythonコードの生成 |
| 使用モデル | DeepSeek |
| 入力トークン数 | 約500,000 |
| 出力トークン数 | 約7,000 |
| 合計料金(参考) | 約0.01ドル |
料金試算のシミュレーション方法
Clineの利用料金を事前に見積もるには、利用したいAIモデルの公式サイトで公開されている料金表を確認するのが最も確実です。 料金は通常、「100万トークンあたり何ドル」という形式で設定されています。
例えば、入力が100万トークンあたり0.1ドル、出力が100万トークンあたり0.2ドルのモデルを使うと仮定します。あるタスクで入力に5万トークン、出力に1万トークン使用した場合の料金は、「(0.1ドル × 5万 / 100万) + (0.2ドル × 1万 / 100万)」という計算式で算出できます。このように、おおよそのトークン消費量を予測することで、かかるコストをシミュレーションすることが可能です。



Clineの種類とそれぞれの特徴を紹介
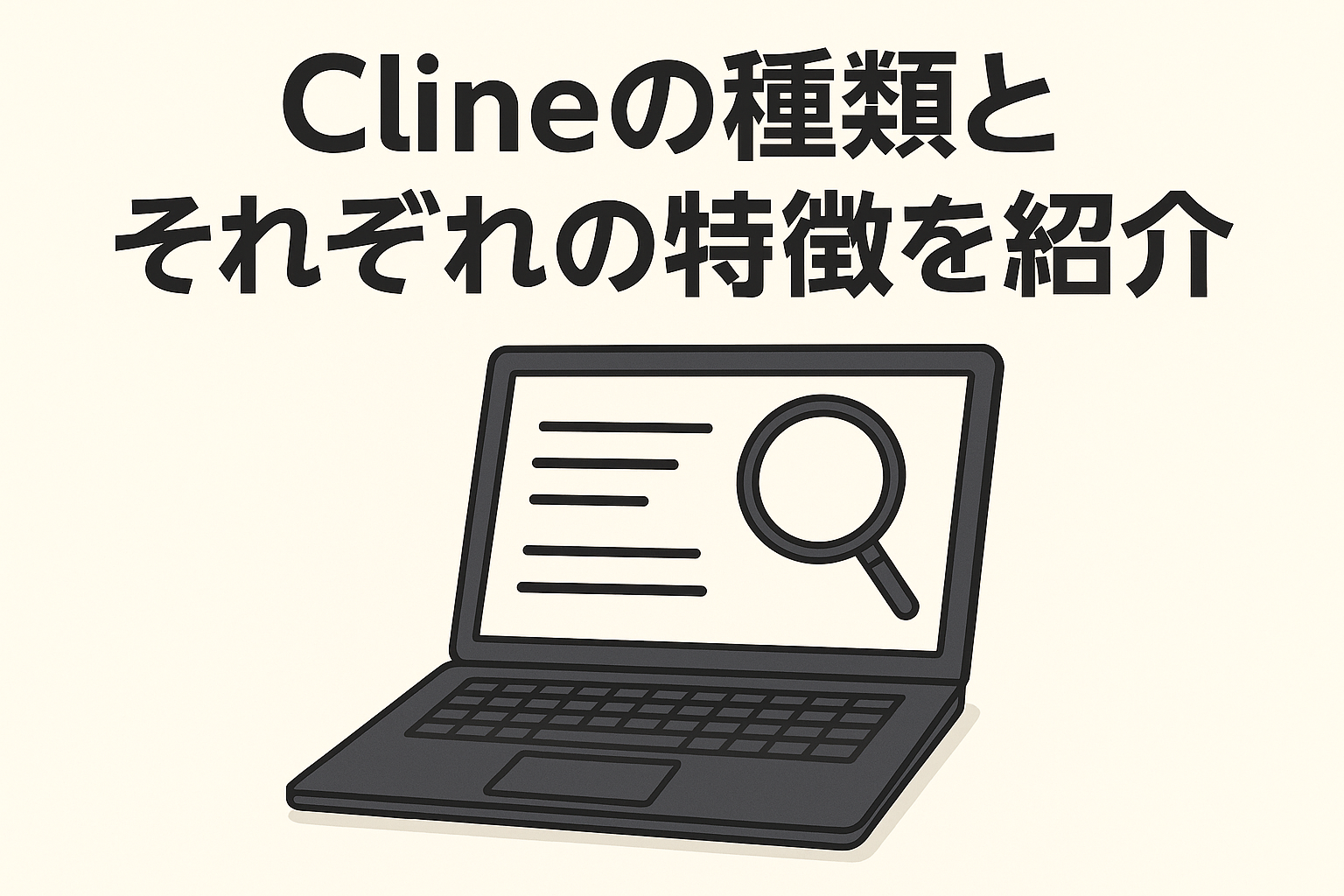
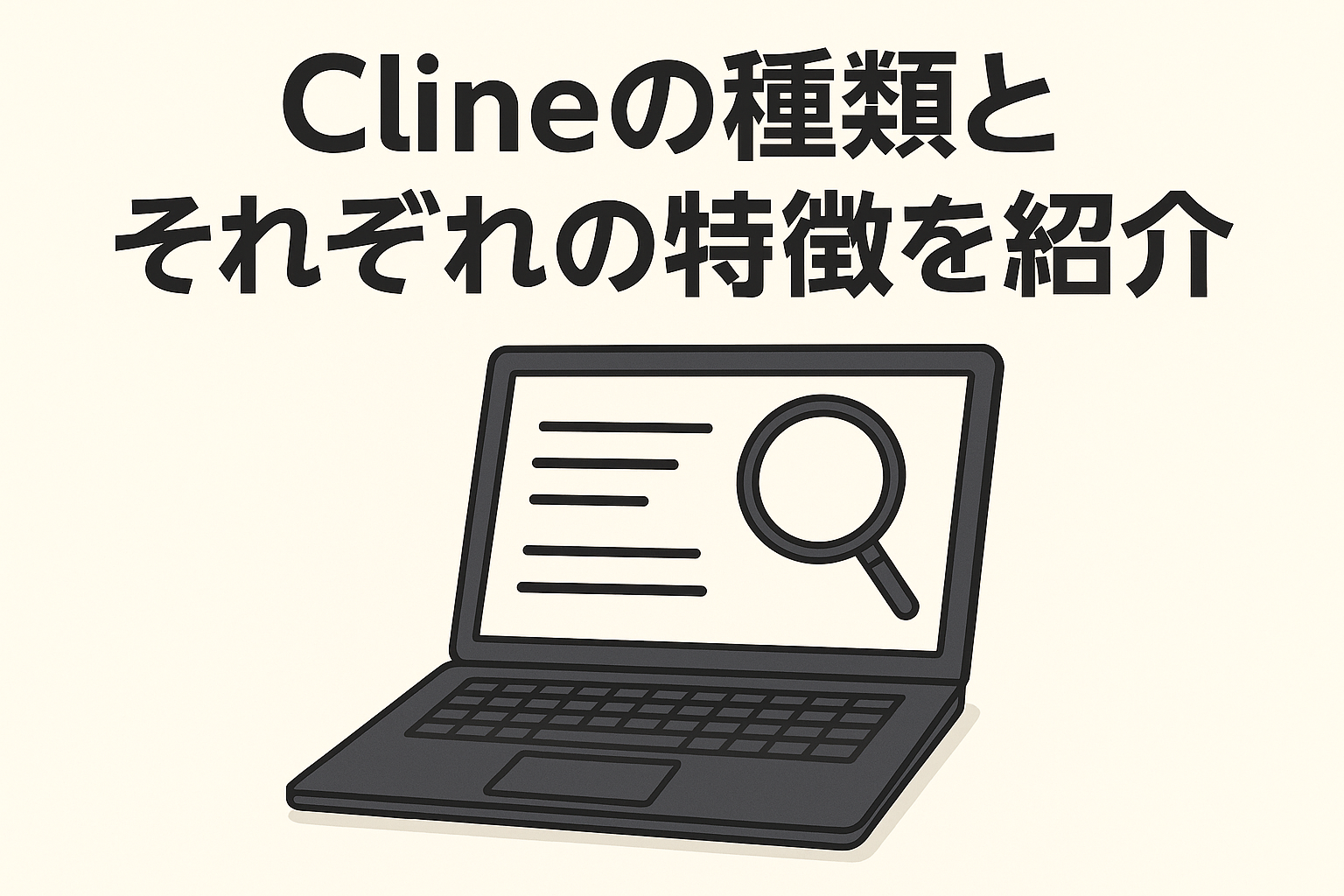
Clineは単一のツールですが、その派生版や関連ツールも登場しており、「Clineファミリー」としてエコシステムを形成しつつあります。 ここでは、ベースとなるCline(旧称Claude Dev)に加え、その発展形と位置づけられる「Roo Cline」や「Cool Cline」、そしてコミュニティ版の「Bao Cline」といったツールの特徴と、それぞれがどのようなユーザーや用途に適しているかを紹介します。
これらの違いを理解することで、あなたの開発スタイルに最も合ったツールを選択する手助けとなるでしょう。
Cline(旧Claude Dev)の基本的な特徴
Clineは、現在広く知られているAIコーディングアシスタントの基本形であり、その前身は「Claude Dev」という名称でした。 オープンソースのVSCode拡張機能として提供され、AIエージェントが自律的に開発タスクをこなすという革新的なコンセプトを打ち出しました。
自然言語による指示で、コード生成からターミナル操作、ブラウザでのテストまでを自動化できるのが最大の特徴です。 様々なAIモデルを柔軟に切り替えられる拡張性を持ち、多くの開発者にとってAI駆動開発の入り口となるツールと言えます。
| 項目 | 特徴 |
| 概要 | VSCode用の自律型AIアシスタント(オープンソース) |
| 主な機能 | コード生成・編集、ターミナル実行、ブラウザ操作 |
| AIモデル | 複数の主要なLLM(GPT, Claude等)に対応 |
| 位置づけ | Clineファミリーのベースとなるツール |
| おすすめユーザー | AI駆動開発を初めて試す、または基本機能を求める開発者 |
Roo Clineの利用シーンと利点
Roo Clineは、ベースとなるClineを拡張し、さらなる高速化や独自機能を追加した改良版と位置づけられています。 特に、定型的な繰り返し作業(Routine Task)の自動化において、その真価を発揮すると考えられます。
例えば、複数のコンポーネントに対して同様の修正を加えたり、定期的にテストを実行してレポートを作成したりといった、決まった手順の作業を効率化したい場合に最適です。Roo Clineは、基本的なClineの機能に加えて、コードアクションのカスタマイズなど、より高度な自動化を実現するための機能が強化されています。
Cool Clineが適する用途とメリット
Cool Clineは、ClineやRoo Code、さらにはコミュニティ版の知見まで取り込んだ、総合的に強化された最新版ツールとされています。 最新の技術(Coolな技術)を積極的に取り入れたプロトタイピングや、複雑なプロジェクト全体を管理するような大規模開発に適しています。
承認フローの自動化や厳密なコスト管理機能なども完備されており、個人開発者だけでなく、チームや組織での利用も視野に入れた設計が特徴です。 最新・最強のAI開発環境を求めるユーザーにとって、Cool Clineは最も魅力的な選択肢となるでしょう。
Bao Clineの特性とおすすめユーザー
Bao Clineは、Cool Clineにも取り込まれているコミュニティ版ツールの一つとされています。 「報告(ほうこく)」という言葉の響きからも連想されるように、特に開発プロセスにおけるドキュメント作成や、コードの仕様を説明する文章の生成といった、テキストベースのタスクに強みを持つ可能性があります。
コードの変更履歴からリリースノートを自動生成したり、複雑な関数の処理内容を分かりやすく日本語で解説させたりといった活用法が考えられます。コードを書くだけでなく、それに付随するドキュメント管理の効率化も図りたいユーザーにおすすめです。



Clineの拡張性・カスタマイズ機能を徹底解説


Clineの真価は、単体で完結する機能だけでなく、その高い拡張性とカスタマイズ性にあります。開発者一人ひとりのワークフローやプロジェクトの特性に合わせて、機能を自由に追加したり、動作を細かく調整したりすることが可能です。
このセクションでは、Clineを自分だけの最強の開発パートナーへと進化させるための、具体的な拡張・カスタマイズ方法について、その核心となる技術とともに深く掘り下げていきます。
MCPを利用したカスタムツールの開発
Clineの拡張性を支える中核技術が「Model Context Protocol(MCP)」です。 これは、Clineが外部のツールやAPIと連携するための標準化された規約であり、あたかもスマートフォンのアプリストアのように、様々な機能を後から追加できます。
例えば、社内のJiraや特定のデータベースに接続するカスタムツールを作成し、「次のタスクに関連するJiraチケットを取得して」といった指示で情報を引き出すことが可能になります。 このMCPを通じて、Clineは単なるコーディング支援ツールから、あらゆるサービスと連携する開発ハブへと進化するのです。
ワークスペースの効率化ポイント
Clineを効率的に活用するには、ワークスペースごとの設定が重要です。プロジェクトのルートディレクトリに「.clinerules」というファイルを作成することで、そのプロジェクト固有のルールをClineに教え込むことができます。
例えば、コーディング規約や使用するフレームワークの作法、特定のファイルは編集しないといった制約を記述します。これにより、AIはプロジェクトの文脈を深く理解し、より的確で質の高いコードを生成するようになります。グローバルな設定とプロジェクト固有のルールを組み合わせることで、ワークスペースの効率を最大化できるでしょう。
開発者向けに提供されるサポート内容
Clineはオープンソースプロジェクトとして開発が進められており、GitHub上で活発なコミュニティが形成されています。 開発者はここで、バグ報告や機能要望、使い方に関する質問などを自由に行うことが可能です。
また、公式ドキュメントも充実しており、導入から基本的な使い方、MCPを利用したカスタムツールの作成方法まで、詳細な情報が提供されています。このようなオープンな開発体制と手厚いドキュメントにより、開発者は安心してClineを利用し、問題が発生した際も迅速に解決策を見つけることができるでしょう。



Clineを活用する際に役立つTips


Clineは非常に強力なツールですが、その能力を最大限に引き出すにはいくつかのコツが必要です。ここでは、多くの経験豊富な開発者が実践している、Clineをより効果的に、そして効率的に使いこなすための実践的なヒント(Tips)をいくつかご紹介します。
これらのテクニックを身につけることで、AIとの共同作業がよりスムーズになり、開発の生産性が飛躍的に向上するはずです。
ルールを整備して効率よく使う
Clineを効果的に使う上で最も重要なのが、ルールの整備です。「.clinerules」ファイルにプロジェクトの規約を詳細に記述することで、AIの出力をコントロールし、手戻りを減らすことができます。
最初にこのルール設定をしっかりと行うことが、AIを優秀なアシスタントに育て、長期的な開発効率を高めるための鍵となります。
- 命名規則(camelCaseなど)
- 使用するデザインシステム
- ファイル分割のルール
- 日本語フォントの使用指定
タスクを小さく分割する工夫
AIに一度に大きすぎるタスクを依頼すると、意図から外れた結果になったり、途中で処理が止まってしまったりすることがあります。これを避けるためには、人間が新人に仕事を教えるのと同じように、タスクを具体的で小さな単位に分割して依頼することが重要です。
例えば、「ログイン機能を実装して」という大きな指示ではなく、「ログインフォームのUIを作成して」「入力されたメールアドレスのバリデーション処理を書いて」「認証APIを呼び出す関数を作成して」のように、段階的に指示を与えることで、AIは各ステップに集中でき、結果として高品質なコードを生成しやすくなります。
プロジェクトドキュメントの上手な活用法
Clineにプロジェクトの全体像や仕様を深く理解させるためには、関連ドキュメントを読み込ませることが非常に有効です。プロジェクトの概要、アーキテクチャ設計、API仕様書などをMarkdown形式で用意し、タスク実行時にClineのコンテキストに含めることで、AIはそれらの情報を基に、より精度の高い判断を下すことができます。
例えば、API仕様書を読み込ませた上で「このエンドポイントを叩く処理を実装して」と指示すれば、仕様に沿った正確なコードを生成してくれる可能性が高まります。
AIリファクタリングを効果的に使う
Clineは、新規コードの生成だけでなく、既存コードの改善、いわゆるリファクタリングも得意としています。まずは自分で要件を満たすコードを書き、その上で「このコードをもっと効率的にして」や「この関数をクリーンアーキテクチャの原則に従ってリファクタリングして」といった指示を出すのが効果的です。
こうすることで、まずは動くものを作り、その後に品質を高めるという効率的な開発サイクルを回すことができます。AIにリファクタリングを任せることで、自分では気づかなかった改善点が見つかることも少なくありません。
AIが動作中は干渉を避ける
Clineがタスクを実行している最中に、人間が手動でコードを編集したり、ファイルを変更したりするのは避けるべきです。なぜなら、Clineはファイルの状態や自身の変更履歴を基に次のアクションを計画しているため、予期せぬ外部からの変更が加わると、処理が混乱し、エラーの原因となるからです。
AIが一生懸命コードを書いている間は、その様子をじっと見守り、処理が完了してから結果を確認し、必要に応じて修正や次の指示を与えるというスタンスが重要です。
メモリバンクを有効活用する方法
Clineには「メモリバンク」という、プロジェクトの重要な情報を長期的に記憶させておくための画期的な仕組みがあります。 これは、セッションが変わると記憶がリセットされてしまうAIの弱点を補う機能です。
プロジェクトの概要や技術スタック、アーキテクチャに関する決定事項などを所定のMarkdownファイルに記述しておくと、Clineはタスク開始時にそれらを読み込み、常にプロジェクトの文脈を理解した上で作業を行ってくれます。 このメモリバンクを整備することで、AIはまるでプロジェクトのベテランメンバーのように振る舞うようになるのです。



Clineを使う際の課題と注意点


Clineは開発効率を飛躍的に向上させる可能性を秘めたツールですが、万能ではありません。現状ではいくつかの課題や、利用する上で注意すべき点も存在します。これらの限界を正しく理解し、適切に対処していくことが、Clineを安全かつ効果的に活用するための鍵となります。
ここでは、開発者が直面しがちな具体的な課題と、その対策について解説します。
ファイルサイズや複雑性の課題
現在のAIモデルには、一度に処理できる情報量(コンテキストウィンドウ)に上限があります。そのため、非常に大きなファイルや、多数のファイルが複雑に絡み合った大規模なプロジェクトを一度に扱わせようとすると、AIが全体像を把握しきれず、性能が低下することがあります。
このような場合は、前述のTipsで紹介したように、タスクを小さく分割したり、関連するファイルだけをコンテキストに含めたりといった工夫が必要になります。
動作確認時に起こりやすい問題
Clineはブラウザやターミナルを操作して、自身が生成したコードの動作確認まで行おうとしますが、このプロセスが常に安定しているとは限りません。例えば、特定の環境変数が必要なテストや、複雑なUI操作を伴うテストでは、うまく動作せずに処理が止まってしまうことがあります。
現状では、AIによる自動テストは補助的なものと捉え、最終的な動作確認は開発者自身が責任を持って行うことが重要です。AIの提案を鵜呑みにせず、必ず自分の目で確認する習慣をつけましょう。
静的型付け言語との相性の注意点
TypeScriptやGoのような静的型付け言語は、コンパイル時に型の整合性をチェックするため、AIがコードを生成する上でのヒントが多く、比較的相性が良いとされています。
一方で、RubyやPythonといった動的型付け言語の場合、AIが文脈から型を推測する必要があるため、時として見当違いなコードを生成してしまうことがあります。動的型付け言語でClineを使用する際は、型ヒントを明記したり、変数名や関数名を分かりやすくしたりするなど、AIがコードの意図を理解しやすくなるような工夫が求められます。
最新技術への対応力に関する懸念
AIモデルの知識は、その学習データが収集された時点までに限定されています。そのため、リリースされたばかりの新しいフレームワークやライブラリについては、知識が追いついておらず、適切なコードを生成できない場合があります。
また、プロジェクト独自のUIフレームワークやライブラリに関しても、AIは当然知識を持っていないため、うまく扱うことができません。このような場合は、必要な情報をドキュメントとして与えるなど、人間がAIを適切に導いてあげる必要があります。



Clineに関するよくある質問
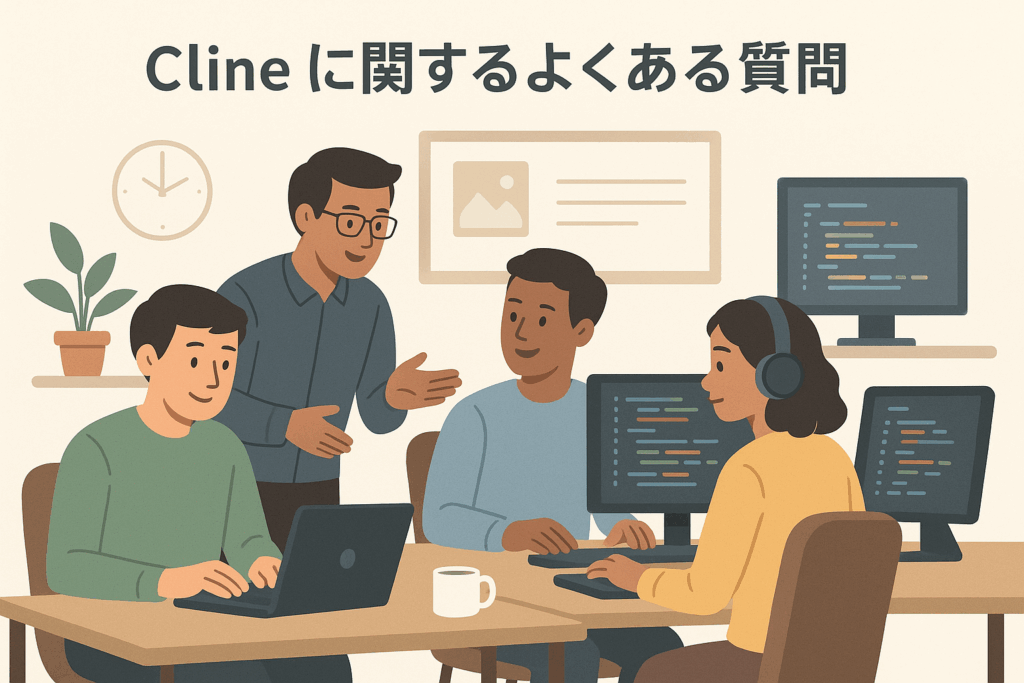
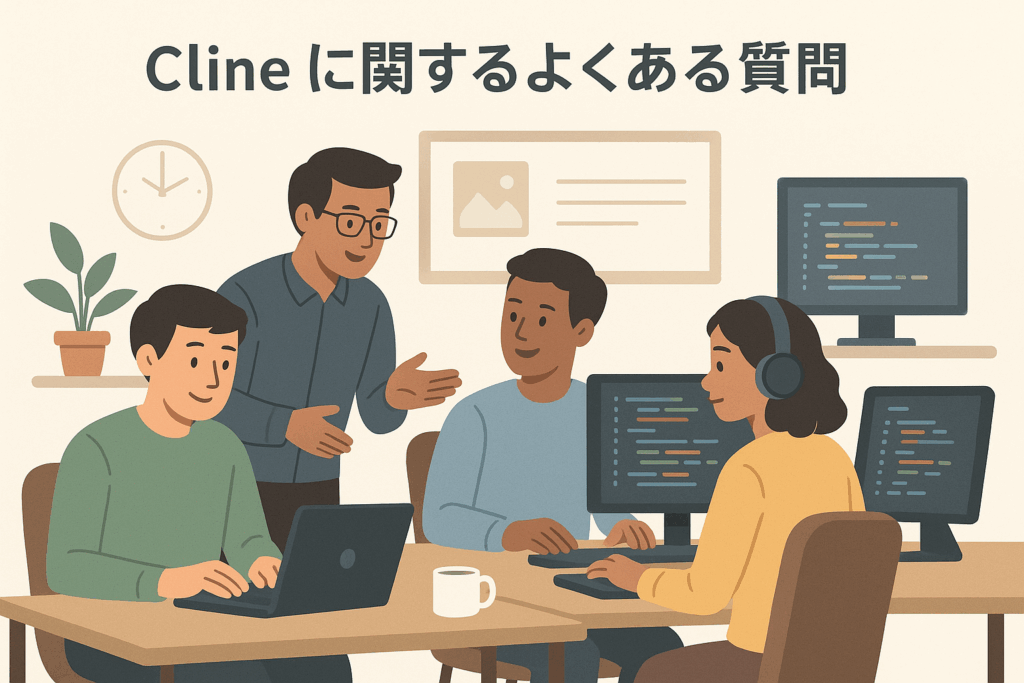
Clineの導入を検討している方や、使い始めたばかりの方から寄せられる、よくある質問とその回答をまとめました。競合ツールとの違いや、安全性に関する疑問など、気になるポイントを解消することで、より安心してClineを活用するための手助けとなれば幸いです。
ClineとCursorは何が違うのか?
ClineとCursorは、どちらもAIを活用した開発支援ツールですが、そのアプローチに違いがあります。 Clineは、VSCodeなどの既存エディタに導入する「拡張機能」であり、柔軟なカスタマイズ性が魅力です。 一方、CursorはAI機能を組み込んだ「専用エディタ」として提供され、よりシームレスなAI体験を目指しています。
どちらが良いかは開発者の好みやプロジェクトによりますが、手軽に始めたい、または環境を自分で作り込みたい場合はCline、オールインワンの環境を求めるならCursorが選択肢になるでしょう。
| Cline | Cursor | |
| 形態 | VSCode等の拡張機能 | AI搭載の専用エディタ |
| 特徴 | 高いカスタマイズ性、モデル選択の自由度が高い | シームレスなAI統合、直感的な操作性 |
| 料金 | API利用料に応じた従量課金制 | 月額/年額のサブスクリプション制 |
| おすすめな人 | 既存環境を変えたくない人、細かくカスタマイズしたい人 | 手軽に最高のAI体験をしたい人、コストを固定したい人 |
Clineの安全性は問題ない?
セキュリティは多くの開発者が懸念する点ですが、Clineはこの点に配慮した設計になっています。 Clineは完全にクライアントサイドで動作する拡張機能であり、あなたの書いたコードがClineのサーバーに送信されることは一切ありません。 APIキーもローカルに保存され、AIモデルとの通信は直接行われます。
また、ファイル変更やコマンド実行は、すべて実行前にユーザーの承認を求める「ヒューマン・イン・ザ・ループ」の思想に基づいているため、AIが勝手に危険な操作を行うのを防ぎます。
ヒューマン・イン・ザ・ループとは?
ヒューマン・イン・ザ・ループ(Human-in-the-Loop, HITL)とは、AIシステムの処理プロセスの中に、人間が介在する仕組みのことです。AIが自動でタスクを進める中で、重要な判断や最終的な承認は人間が行うことで、システムの安全性と信頼性を高めるのが目的です。
Clineにおいては、AIが提案したコードの変更やコマンドの実行を、ユーザーが「Approve(承認)」して初めて実行される仕組みがこれにあたります。 これにより、AIの暴走を防ぎ、開発者はAIの提案をコントロールしながら、その恩恵を受けることができるのです。



まとめ|Clineの特徴と活用方法を理解しよう
本記事では、AIエージェント型開発支援ツール「Cline」について、その基本機能から具体的な使い方、料金、拡張性、そして活用するためのTipsや注意点まで、網羅的に解説してきました。Clineは、単なるコード補完ツールではなく、開発者の指示に基づき、ファイルの作成・編集、コマンド実行、さらにはブラウザ操作まで自律的にこなす、まさに次世代の開発パートナーです。
タスクを駆動するAI支援、複数のAIモデルとの連携、そしてMCPによる高い拡張性は、あなたの開発ワークフローを根本から変える力を持っています。 もちろん、ファイルサイズの問題や最新技術への追随など、まだ課題も残されています。しかし、タスクを小さく分割したり、ルールやメモリバンクを整備したりといった工夫を凝らすことで、その能力を最大限に引き出すことが可能です。
この記事を参考に、あなたもClineを導入し、面倒な定型作業をAIに任せ、より創造的で価値の高い仕事に集中することで、開発者としての新たなステージへと駆け上がってください。